40代にとってご自分の健康も確かに気になることですが、親御様の介護の問題について大事なことは何んとなく感じているのですがよくわからないことが多く、実感が薄いので逆に心配なことではないでしょうか。
「介護の場面は想定してない時に突然直面して困った」という話はよく話題になることで、聞いたことがある人も多いと思います。
この記事では、いずれ起こりえる不安がある人に「40代から介護のもしもに備えましょう」ということを紹介しています。
- 【第1章】介護 もしも 備え|“心の準備”は妻との会話から始まった
- 【第2章】親の介護 事前準備|40代が実家で始めた“やわらかい家族会議”
- 【第3章】40代 家族会議 介護|家族の価値観をすり合わせる時間を持つ意味
- 【第4章】介護保険 確認 方法|公的制度の基本と“いざというとき”の対応手順
- 【第5章】介護 書類 まとめ|見落としがちな「情報の整理」とその保管法
- 【第6章】エンディングノート 書き方 実例|感謝と希望を綴る“もしもノート”
- 【第7章】親が倒れたら 何から始める|行政機関との最初の連携と相談のコツ
- 【第8章】介護施設 選び方 ポイント|後悔しないための見学・確認チェックリスト
- 【終章】40代 介護 準備|“いつか”に備えることは、今を大切にすることだった
【第1章】介護 もしも 備え|“心の準備”は妻との会話から始まった

「もし、お義父さんに何かあったら、どうするつもりだったの?」
その一言が、健一(仮名)の心に静かに突き刺さった。
45歳、会社では中間管理職。家庭では高校生の息子と小学生の娘を育てる父親。そして、遠方に暮らす70代の両親はまだ元気で、電話をすれば笑い声も聞こえてくる。
だからこそ、“介護”なんて言葉は、自分にはまだ遠い世界のことだと思っていた。
だがある日、父・昭夫が軽い熱中症で倒れ、近所の人の通報で救急搬送されたという連絡を受けた。幸い大事には至らなかったが、その報せに動揺した自分がいた。
その晩、食事の後のリビングで、妻の恵美がぽつりとつぶやいた。
「私たち、本当に何も準備してないね。いざという時、どう動けばいいのか、全然分からないよ」
健一は言葉に詰まった。たしかに、両親の健康状態、保険や年金のこと、万が一のときの連絡体制――何一つ話し合ったことがなかった。
■「介護の備え」とは、制度や施設ではなく“心の準備”から始まる
健一は翌日から、昼休みにスマホで「介護 もしも 備え」と検索を始めた。介護保険や施設選び、費用のことなど、情報は山ほどあったが、どれも“もっと先の話”のように思えてしまった。
そんな中、ある記事の一文が目に留まった。
「介護の準備は“書類”や“お金”の前に、“気持ち”の整理から始まる」
この言葉に、健一は少し救われた気がした。たしかに、完璧な準備なんて最初からできるわけがない。でも、「まず心の準備をしておく」というだけなら、今からでも始められるかもしれない。
その夜、健一は妻と改めて話し合った。
「なんかさ、俺たち、何かあったら動けるように、ちょっとずつ話をしておいた方がいいかもな」
恵美はうなずきながら、「うん、ゆるくでいいから、まずは“考え始める”だけでも安心感が違うよね」と言った。
■“考え始める”だけで、行動が変わる
こうして健一の「介護に備える生活」が静かに始まった。
大きな一歩ではなく、ほんの小さな変化。まずは「自分が知らないことが多すぎる」という事実を受け入れ、次に、「知ろうとする姿勢」を持つことから。
そしてなにより、「もしも」を口に出す勇気が、家族とのつながりを深めるきっかけになる。
【第2章】親の介護 事前準備|40代が実家で始めた“やわらかい家族会議”

「そんなに心配しなくても、まだ元気だよ」
父・昭夫は笑ってそう言ったが、健一にはその笑顔が少し心細く見えた。
週末を使って帰省した健一は、母・美智子の作った昼食を食べながら、両親とゆっくり話す時間を持った。
特に大きな理由があったわけではない。ただ、前回の熱中症の件以来、どこか気になっていた「介護のもしも」を、やんわりと切り出してみたかったのだ。
■「親の介護 事前準備」は、雑談のような“日常会話”から
「この前ちょっと倒れたって聞いて、びっくりしたよ。…将来のこと、少し考えたりしてる?」
沈黙が流れるかと思ったが、母・美智子が意外とあっさり返してきた。
「そうねえ、入院とかになったら、どこに連絡すればいいとか、あんたたち分からないわよね」
この瞬間、健一は“扉が開いた”感覚を覚えた。
父も「まだ元気だけど、まあ、いつまでもとはいかんからな」と小さく笑い、次第に家族の将来を話すムードに変わっていった。
ここで健一が意識したのは、「介護」という言葉を最初から使わなかったこと。代わりに「将来どうしたいと思ってる?」「困ったとき、誰に連絡すればいい?」など、“日常の延長線上の会話”を心がけた。
■事前準備は「想いの共有」から始まる
両親と話していて分かったことがある。それは、「介護施設に入りたくない」「できれば自宅で過ごしたい」など、思っていても口にしていない願望が意外とあるということだ。
美智子は「誰にも迷惑かけたくない」と何度も口にしたが、健一は「迷惑かけるのが当たり前だよ。だから準備しておこう」と伝えた。
親も子も、「言いにくいことを言える関係」になっておくことが、実は最大の備えなのかもしれない。
■やわらかく話す“家族会議”のすすめ
健一はその後、妻と相談し、自宅でも“家族会議”を開催した。高校生の翔太と小学生の未来にも、「じいじとばあばのこと、これから少しずつ考えていくよ」とやさしく説明。
子どもたちも最初はポカンとしていたが、「家族って、困ったときに助け合えるってことだよ」と伝えると、素直にうなずいてくれた。
親の介護の事前準備は、いきなり制度や施設の話をすることではありません。まずは「お互いに思っていることを少しずつ共有する」こと。それが、健一にとっての最初の一歩になりました。
【第3章】40代 家族会議 介護|家族の価値観をすり合わせる時間を持つ意味

家族で介護について話すというと、どうしても“重たい話題”のように感じてしまう。だが健一は、両親との会話をきっかけに「もっと気軽に、だけどきちんと」話せる場を持ちたいと考え、自宅での“家族会議”を定例化することにした。
ある日曜日の夜。リビングに家族4人が集まり、テレビを消して静かな時間が流れた。
「今日は、じいじとばあばのことを少し話そうと思ってるんだ。将来、何かあったときに、みんなでどう動けばいいかっていう話」
健一の言葉に、息子の翔太が「うん」とうなずき、娘の未来も「学校でも“家族のこと考えよう”って授業でやったよ」と明るく返した。
■価値観の“ズレ”を放置しない
この家族会議で健一が大切にしたのは、「誰かの意見を否定しないこと」。
恵美は「施設に入ってもらったほうが安心」と考えていたが、健一は「できれば自宅で」と感じていた。
翔太は「学校の勉強があるから、僕はあんまり手伝えないかも」と正直に言い、未来は「わたし、ごはん作るの手伝うよ!」と張り切った。
それぞれの立場や年齢、考え方が違うからこそ、価値観の“すり合わせ”が必要だった。
■共有することで、家族が「チーム」になる
介護は一人ではできない。けれど、誰が何を担うかを話し合っておくことで、“なんとなく”の不安が“見える計画”に変わる。
健一はメモを取りながら、家族で出た意見をノートにまとめていった。
- 「連絡担当はパパ」
- 「手続きはママが調べておく」
- 「翔太はテスト期間中は免除」
- 「未来はお見舞い係」
たとえ今すぐ必要でなくても、「自分たちは考えている」という共通認識が生まれることで、家族の一体感が強まっていく。
健一は思った。備えとは、“形ある準備”だけでなく、“心の役割分担”でもあるのだと。
【第4章】介護保険 確認 方法|公的制度の基本と“いざというとき”の対応手順

ある平日の昼休み、健一は「要介護認定」という言葉が気になり始めていた。もし親が倒れたとき、すぐにどこかへ電話して何か申請すればいいのか? それとも病院から何か案内があるのか?
スマホで「介護保険 確認 方法」と検索すると、複雑な制度や申請の流れが並んでいた。
「これは、一度ちゃんと聞きに行ったほうが早いな」
そう思った健一は、昼休みを使って市役所の介護保険課に立ち寄ることにした。
■最初に相談すべきは「地域包括支援センター」
市役所で案内されたのは、自宅近くの「地域包括支援センター」。介護が必要になりそうな高齢者やその家族のための総合相談窓口だ。
センターの担当者は丁寧にこう教えてくれた。
「要介護認定の申請は、本人か家族が市区町村に申請することでスタートします。その後、認定調査員が訪問し、医師の意見書とあわせて審査会で認定の等級が決まります」
健一は、知らなかった情報が多すぎることに軽くショックを受けた。だが同時に、「今、聞いてよかった」とも感じた。
■いざというときに備えて“確認”しておくべき制度と流れ
健一が地域包括支援センターで得た情報を、自宅でまとめたメモにはこう書かれていた。
- 要介護認定の申請 → 市区町村の窓口または包括支援センター
- 調査と医師の意見書をもとに審査
- 認定までに通常30日ほどかかる
- 認定を受けたらケアマネジャーと「ケアプラン」を作成
- デイサービス・訪問介護などの介護サービスが利用可能に
「親が倒れてから考えたんじゃ遅い。せめて、この流れだけは家族で共有しておこう」
健一は、家族会議でこの情報を簡単に説明し、メモをGoogleドライブに保管。誰でもアクセスできるようにした。
■「知っている」だけで、安心感は何倍にもなる
介護の現場では、知らなかったがために損をするケースが少なくない。サービスの利用が遅れたり、手続きに時間がかかって本人に負担がかかることも。
だが、制度の全貌を理解する必要はない。
「何を、どこで、誰に聞けばいいか」さえ知っていれば、慌てずに行動できる。
健一は思った。介護の備えとは、知識で未来の不安を少しずつ減らしていくことなのかもしれない。
【第5章】介護 書類 まとめ|見落としがちな「情報の整理」とその保管法
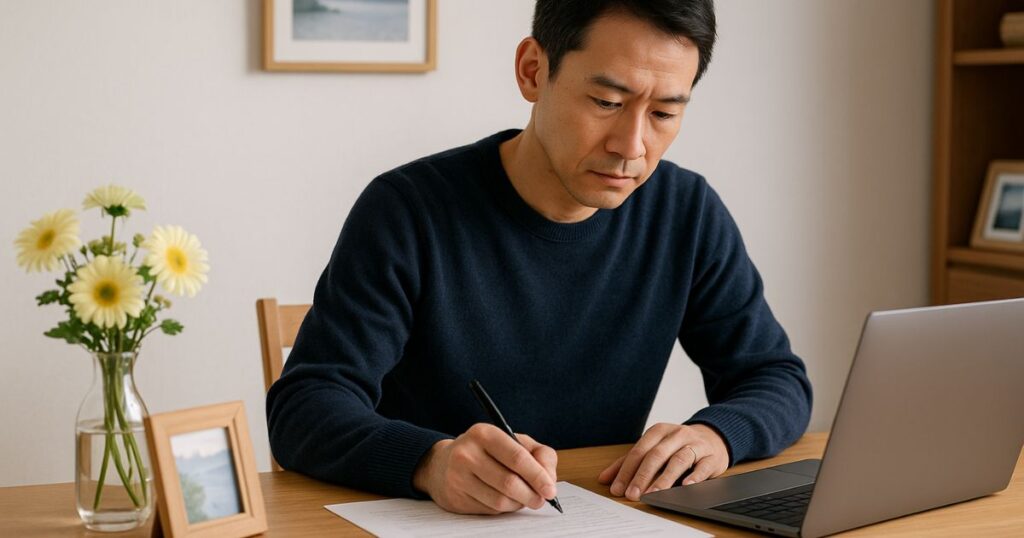
介護の制度を少しずつ理解し始めた健一が、次に取り組んだのは「情報の整理」だった。
「そもそも、親の保険証や年金手帳って、どこにあるんだろう?」
ふとした疑問から始まり、健一は母・美智子に連絡を入れた。美智子は「いろいろ押し入れに入ってると思うけど…」と、あいまいな返事。
実家に戻った週末、押し入れの中から古い封筒や書類の束が出てきた。だが、何がどれに使うものなのか、整理されておらず、見つけるだけでひと苦労だった。
■最低限まとめておくべき介護関連の書類とは?
健一はネットで調べたリストを元に、以下の書類をチェックし始めた。
- 健康保険証、介護保険証
- 年金手帳、年金振込通知書
- 預貯金通帳、印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)
- 生命保険や医療保険の証券
- 医療情報(かかりつけ医、服薬情報)
これらの書類がバラバラに保管されていると、いざというとき家族が把握できず、大きなストレスになる。
「せめて“見える化”しておこう」
健一はクリアファイルとインデックス付きのバインダーを購入し、書類を種類ごとに分類した。
■デジタル化+共有で“迷子の書類”をゼロに
紙の書類だけでは不安だったため、健一はスマホで各書類をスキャンし、Google Drive上に「介護関連」としてフォルダ分け。
- 両親それぞれのフォルダを作成
- 家族全員が閲覧できるよう共有設定
- 更新日や内容のメモも付記
「誰か一人が全部知ってる」状態ではなく、「誰でも必要なときに見られる」状態へ。
これだけでも、介護の初動が驚くほどスムーズになると、地域包括支援センターの担当者も教えてくれた。
■「知らなかった」から「整理してある」に変えるだけで家族が安心する
美智子は、整ったファイルを見て少し恥ずかしそうに笑った。
「なんか…ちゃんとしてるって感じがして、安心するね」
情報の整理は、単なる事務作業ではない。親のため、家族のため、そして将来の自分自身のためにできる、もっとも身近で確実な“備え”の一つだ。
健一は、少しずつ形になっていくこの準備に、手応えと自信を感じ始めていた。
【第6章】エンディングノート 書き方 実例|感謝と希望を綴る“もしもノート”

健一が“情報の整理”を終えた頃、母・美智子から電話があった。
「ねえ健一、これからのこと、ノートに書いておこうと思うの」
少し照れくさそうに話すその声に、健一は驚きつつも嬉しくなった。まさか、自分から話す前に母の方が行動に移してくれるとは思っていなかったのだ。
■エンディングノートは“死”の準備ではなく“生き方”の表明
多くの人が、エンディングノートと聞くと「終末期」や「相続」といったネガティブな印象を抱きがちだ。
だが実際は、自分の意志や想いを“伝える”ためのノートであり、家族の不安を減らすための有効な手段でもある。
母・美智子が書き始めたノートには、以下のような項目が記されていた。
- 医療に関する希望(延命治療の可否など)
- 財産の大まかな内容と保管場所
- かかりつけ医や服薬情報
- 葬儀やお墓に関する希望
- 家族への手紙
読みながら、健一の胸に温かい気持ちが広がった。
「これ、僕も書いてみようかな…」
そう思った健一は、自分用にもノートを買い、少しずつ書き始めた。
■40代でも“もしもノート”を持つ意義
介護に直面する立場であると同時に、自分自身もいつどうなるか分からない年代。
健一は、まだ若いと思っていた自分の“立ち位置”を見つめ直し、「もし自分に何かあったとき、家族にどうしてほしいか」を書き記すようになった。
翔太や未来には「お父さん、ちゃんと考えてるんだね」と尊敬の眼差しで見られ、妻の恵美も「こういうのがあると、心が落ち着くね」と言ってくれた。
■エンディングノートは、家族をつなぐ“感謝の記録”になる
ノートに書く内容は形式的なものだけでなく、「ありがとう」「愛している」「任せたよ」といった、普段は照れくさくて言えない気持ちも含まれる。
それは、ただの書類ではない。 家族の心に残る、“未来への贈り物”になる。
健一は、母のノートをきっかけに、介護の準備が単なる対策や段取りではなく、人と人との想いのつながりを強くする時間なのだと気づき始めていた。
【第7章】親が倒れたら 何から始める|行政機関との最初の連携と相談のコツ

ある土曜日の朝、健一のスマホに母からの着信があった。
「お父さん、さっき急に倒れちゃって…今、救急車で病院に向かってるの」
突然の事態に心臓が締め付けられる思いだったが、これまでの備えが健一の冷静さを支えた。
妻に子どもたちのことを任せ、健一はすぐに病院へ向かった。
■まずは病院での説明と入院手続き
病院で父の状態を確認。幸い命に別状はなかったが、しばらく入院が必要という診断だった。
担当医から説明を受け、入院手続きを進めながら、健一は次に何をすべきか頭の中で整理を始めた。
「もし今後、自宅での生活が難しくなったら?」
このときこそ、行政機関との連携が必要なタイミングだった。
■地域包括支援センターに連絡を
まず連絡したのは、以前訪れた地域包括支援センターだった。父の状況を伝えると、以下の手続きを提案された:
- 要介護認定の申請
- 入退院後の生活環境確認
- 必要であればケアマネジャーの選定
「お父さまの状態が安定したら、病院の退院調整部門と連携して、今後のプランを一緒に考えていきましょう」と職員が丁寧に説明してくれた。
■退院前に“調整”しておくこと
退院が決まる前に、やっておくべきことがある。
- 自宅での生活に戻れるかどうかの確認(バリアフリー・見守り体制)
- 必要な福祉用具の選定と手配(ベッド、手すり、車椅子など)
- 家族の支援体制の確認(誰がどこまで対応できるか)
病院・家族・行政が三位一体で動けるようにすることが、円滑な介護生活のスタートにつながる。
■「ひとりで抱えないこと」が一番のコツ
健一は今回の件で痛感した。介護の初動で一番大切なのは、「ひとりで何とかしようとしない」こと。
手続きや制度の理解、施設探し、生活環境の見直し――すべてを自分ひとりで抱え込むのは無理がある。
「頼っていい場所」が分かっていたことで、健一は無理なく、必要な支援を受けることができた。
これは、事前に一歩踏み出していたからこそ得られた安心だった。
【第8章】介護施設 選び方 ポイント|後悔しないための見学・確認チェックリスト

父・昭夫の退院が現実味を帯びてきたある日、医師から「今後の生活が今まで通りとはいかないかもしれません」と告げられた。
在宅での介護も可能だが、家族の負担や安全面を考え、介護施設の利用という選択肢が浮上した。
健一はさっそく、地域包括支援センターから紹介されたいくつかの施設をリストアップし、見学予約を取り始めた。
■まず知っておきたい施設の種類と特徴
担当者から説明された介護施設の主な種類は以下の通り
- 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上で入居可、公的施設のため費用は比較的安いが、空き待ちが長い
- 介護付き有料老人ホーム:要介護度に応じた手厚い介護、費用は中〜高額
- グループホーム:認知症の高齢者向け、家庭的な環境、地域密着型
それぞれにメリット・デメリットがあり、家族の希望・予算・介護度に合わせた選定が求められる。
■見学時にチェックすべきポイント
健一は妻・恵美とともに、実際に2つの施設を見学した。
施設ごとに感じた印象の違いが大きく、「見学せずに決めていたら…」と冷や汗をかく場面も。
見学時には、以下の点を必ずチェックするようにした:
- スタッフの挨拶や表情、利用者への対応
- 清掃状況や臭い、設備の清潔感
- 食事内容や食堂の雰囲気
- 面会や外出のルール、入居者の自由度
- 緊急時の対応体制(夜間の人員配置など)
「見ればわかる」こと、「聞かなければわからない」こと、その両方が施設選びには欠かせなかった。
■比較表を作成して、家族で共有
帰宅後、健一はExcelで施設比較表を作成した。
| 項目 | 施設A | 施設B |
|---|---|---|
| 月額費用 | 約18万円 | 約15万円 |
| 対応スタッフ | 24時間常駐 | 夜間1名体制 |
| 食事対応 | 常食・刻み食・アレルギー対応可 | 常食のみ |
| 面会ルール | 予約制、月4回まで | 自由、時間制限あり |
| 雰囲気 | 明るく活気あり | 静かで落ち着いた印象 |
こうした一覧にすることで、家族全員が客観的に比較でき、意見のすり合わせもスムーズに。
■「施設を選ぶ」は、「家族の未来を選ぶ」こと
介護施設選びは、単なる“入居先探し”ではない。
家族の生活リズム、心理的な安心感、本人の尊厳…すべてに関わる大切な決断だ。
健一は、父が「ここなら安心して過ごせそうだな」と笑った瞬間、涙が出そうになった。
“選んだ”のではなく、“納得できる選択を一緒にした”――それが、介護の現場において、もっとも大切なことかもしれないと感じた。
【終章】40代 介護 準備|“いつか”に備えることは、今を大切にすることだった

父・昭夫の介護にまつわる一連の出来事を経て、健一の心にはある確信が芽生えていた。
「備えることは、先の不安に対する“予防接種”のようなものなんだな」
最初は漠然とした不安だった。自分に介護なんてまだ早いと思っていた。だが、少しずつ知ることで、話すことで、準備することで、不思議と心は穏やかになっていった。
■“もしも”は、思ったよりも早くやってくる
父が倒れた日の朝、健一は“準備していて本当によかった”と実感した。
事前に調べておいたこと、家族で共有していた情報、行政への連絡先、そして何より「慌てなくていい」という精神的な備えが、すべてを助けてくれた。
そして、施設選びまでを終えた今、健一は新たな視点で“これから”を見つめている。
「親のことだけじゃない。自分も、いつかは誰かに助けられる立場になる。そのとき、子どもたちに“どうしてほしいか”を伝えられる父親でいたい」
■備えることは、“今”を生きる力になる
介護の備えとは、決して未来を悲観することではない。むしろ、未来を見据えて“今をよりよく生きるための準備”だ。
- 不安なまま過ごすより、少しでも知っておく
- 一人で抱えるより、家族で話し合う
- 書き出しておくことで、心が整う
それが、日々の生活に安心をもたらし、家族の絆を深め、今を大切にする意識へとつながっていく。
■あなたも、今日から“できること”をひとつ始めてみませんか?
健一のように完璧に準備する必要はありません。
- 「実家の書類、どこにあるんだろう?」と考えること
- 「親と何を話しておこう?」と少し気にかけること
- 「市役所の相談窓口って、どこだっけ?」と検索してみること
そのどれもが立派な第一歩です。
「40代の今こそ、“いつか”に備えるチャンスです」
この記事が、あなたの大切な家族と未来のための“きっかけ”になることを願って。
今回の登場人物は主人公である健一、その妻:恵美、主人公の父親:昭夫、母親:美智子と主人公の子供:翔太と未来という、よくある家族構成の一家の物語として表現させていただきました。
ごく普通の家族の家庭で起こりえる「介護への不安」と「いざという時の備え」をテーマに構成しています。
登場人物はすべて架空のものですが、ごく普通の家族の家庭で起こりえる「介護への不安」と「いざという時の備え」をテーマに構成しています。
ぜひあなたの大切なご家族の介護の備えに役立てていただければ幸いです。




